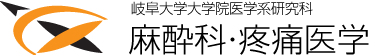研究・業績
臨床研究や基礎研究など、様々な視点を生かしながら、
明日の臨床に役立つことを願って研究活動をしています。
研究概要
最近の研究の紹介
基礎研究紹介
1. 痛みに関する研究
A.術後痛に関する研究
手術によって組織や神経が損傷したり,損傷部位に炎症が起きることにより急性術後痛が生じます.しかし,何らかの原因により慢性化し,難治性の術後痛を呈することがあることが知られていますが,その発症機序や原因となる因子など多くが不明のままです.我々は,実験動物を用いて術後痛モデルを作製し,術後痛の発症機序や原因物質を解明することによって,新たな治療法の確立に役立てたいと考えています.
B.周術期における痛み治療に関する研究
近年,周術期において末梢神経ブロック(PNB)は広く用いられるようになっています.特に術後痛のコントロールにおける末梢神経ブロックの有用性は高いと考えられていますが,明確な作用機序は不明です.基礎研究によって,末梢神経ブロックに使用される薬剤・時間・場所などを明らかにすることで,末梢神経ブロックのエビデンスを確立したいと考えています.また,実験動物を用いて,術前・術後における疼痛治療の1つとして漢方薬やアロマオイルなどの代替医療に対するエビデンスの確立のために検討を行っています.
当科では,これまでの行動実験や組織学的実験だけでなく,in vivoイメージングを用いた痛みの評価を計画しています.この方法は運動に障害があり,行動実験では痛みの評価が困難なモデル動物の痛みの評価に活用できる可能性があり,今後の発展に期待しています.
2.神経炎症に及ぼすグリア細胞の役割・神経炎症に対する分子防御機構の解明
神経炎症は感染による炎症性神経疾患のみならず,神経変性疾患,虚血性疾患,認知機能障害,神経障害性疼痛における中枢性感作などにおいても,重要な役割を果たしていることが明らかとなってきています.神経炎症は主に神経系におけるマクロファージに相当するミクログリアが関与しているとされていますが,神経細胞の隙間を埋め,神経組織の構造を保ったり,神経伝達物質のシナプスからの回収を担っているとされるアストロサイトも重要な役割を果たしていることがわかってきました.当教室ではこれまで,神経炎症が惹起される機序を、培養アストロサイト内の細胞内情報伝達の詳細を明らかにすることによって解明してきました.
また,臓器・細胞が様々なストレスにさらされると発現し,再度のストレスに対する耐性を獲得できるようになるための分子であるheat shock protein (HSP)が神経炎症に関与していることから,炎症性サイトカインとHSPの関係を検討しています.
臨床研究紹介
岐阜大学では麻酔記録にフィリップス社のORSYS®を使用していますが,合わせてViPros®というデータ管理ソフトを実装しています.ViPros®を活用することでこれまで行ってきた麻酔の記録からデータを抽出し,後ろ向き研究を行うことが可能となっています.紙谷が赴任してから,末梢神経ブロックを併用した全身麻酔が様々な手術で適用されるようになりましたが,脳外科手術における頭皮ブロック,腹腔鏡下手術におけるアプローチの異なる腹壁ブロックの術後鎮痛に及ぼす影響を明らかにしてきました.また,電子カルテからのデータ取得もCrista! ®というデータ抽出ソフトを実装していることから,術前・術後の状況と術中のデータを突き合わせて解析することが可能です.少しずつですがこれまで行ってきた臨床麻酔から,埋もれていた新たな発見をしていきたいと考えています.
前向き研究としては分離肺換気中のrSO2の変化や気管支カフ内圧の変化の調査を行ってきましたが,現在進行中のものとして化学療法により惹起される末梢神経障害の程度を定量化できないかの検討を行っています.また,末梢神経ブロックに関するいくつかの前向き研究も実施に向けて研究計画を詰めています.さらに人工心肺の使用により血小板機能にどのような影響が出るのかを分子レベルで検討する臨床研究を開始する予定です.
医師は公共の福祉に応えるために研究者としての側面も持っています.岐阜大学麻酔科ではまだまだ発展が見込まれる臨床麻酔・疼痛医学の分野でエビデンスを創出すべく,努力を怠りません.それらの研究が医局員個々人のキャリアアップにつながることはもちろん,麻酔科全体のレベルアップに資するだろうと考えています.直近の目標として研究を通じて学位取得を目指すのも良いでしょう.当科では社会人大学院生として,スタッフとして勤務しながら学位取得を目指す若手・中堅麻酔科医を最大限サポートします.
今までの研究の紹介
臨床研究
1. 遷延性術後痛
開胸手術後の術後痛の遷延化を亜急性期から介入することにより減少させることが出来ることを明らかにした(吉村)。現在、他大学と協力して肺・膝関節術後の痛みを後ろ向きに検討し、遷延性術後痛の発症率と危険因子を明らかとした。今後は前向き調査を行いより詳細に危険因子を検討する予定(代表:杉山)。
2. オピオイド感受性と遺伝子多型
岐阜薬科大学と共同でオピオイドに対する感受性と遺伝子の関連を検討している。将来、オピオイド少量投与に対する反応からオピオイド感受性が簡単に推測でき、治療方針の決定に寄与できることを目標としている(杉山)
3. MEP施行手術の麻酔方法
現在MEPを行う手術では静脈麻酔が主流である。しかし、吸入麻酔薬であっても十分にMEPは描出され得ることを示してきた。脊椎・脊髄外科手術を対象とし、特に長時間の手術においてはMEPの経時的評価にあたり静脈麻酔薬よりも吸入麻酔薬が優れているのではないかと考え実証しようとしている(福岡)
4. その他
ペインクリニック外来、周術期ともに日常のちょっとした疑問から様々な研究を行っている。
基礎研究
1. 脳循環
cranial window、spinal windowを用いて脳脊髄の血管を直接観察する手法を確立し、各種薬剤の影響や様々な状態変化に伴う脳脊髄血管の変化を報告してきた。現在は、高血糖が脳血管に及ぼす影響とその機序や、高血糖に対する脳血管の反応に麻酔薬により差があるかどうか(鬼頭和裕、阪田)を検討している。
2. 基礎研究
薬理学教室と共同で血小板、アストロサイトの機能とその細胞内情報伝達を研究、これまで様々な報告を行っている。
血小板:術前の禁煙や抗血小板薬休薬が血小板機能に与える影響とその機序の検討(飯田祐子、大沼)
アストロサイト:脳虚血時にアストロサイトから産生されるサイトカインの産生・遊離機序と麻酔薬がそれに与える影響とその細胞内情報伝達の解明(田辺)
当教室では臨床研究、基礎研究ともに他分野、他施設との共同研究に積極的に参加したいと考えています。気軽に声をおかけください。
Copyright © 岐阜大学大学院医学系研究科 麻酔科・疼痛医学. All right reserved.